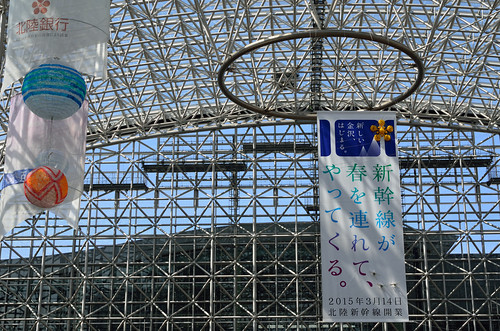大学の新入生コンパの帰り、初めての酒の酔いの胸苦しさに祇園・白川の巽橋の橋詰に佇み、川風で顔の火照りを冷ましていると、傍らの歌碑にふと目が止まった。

「かにかくに祇園はこひし寝るときも枕の下を水のながるる」
吉井勇の歌だった。その瞬間、言いようのない喜びが込み上げてきた。京都で文学に打ち込めるという期待に満ちた喜びだった。
それから三十数年、八尾高校へ赴任となり、新任の挨拶で同窓会長宅の老舗旅館を訪れると、その門前の歌碑に目を奪われた。
「旅籠屋の古看板に吹雪して飛騨街道をゆくひともなし」
吉井の歌だった。
その時、私の胸中で京都の青春と八尾が直結し、八尾の町が輝いた。
挨拶を終え、しばらく歩くと、曳山展示館の前の歌碑に
「この町のとりわけひとり善人の秋路笛吹く月夜あかりに」
「吾もいつか越びとさびぬ雪の夜を八尾の衆と炉端酒酌む」
「山の町秋さびし町屋根の上に石のある町八尾よく見む」
これも吉井の歌だった。

更に足を伸ばし、城山に登ると、
「君のする古陶かたり聴きてゐぬ越の旅籠に春を待ちつゝ」
そこにも吉野の歌碑があった。
八尾の町の至る所に吉井の気配がした。その時ようやく気が付いた。吉井は戦争末期の昭和20年2月から10月まで京都から八尾に疎開し、その間、宮田旅館、常松寺、小谷氏宅と転々と居を移していた。その8カ月間を詠んだのが歌集「寒行」の末尾と「流離抄」(共に昭和21年)だった。宮越の本法寺境内にも彼の
「古寺に大曼陀羅を見にゆきしおもひでひとつ残し秋来ぬ」
の歌碑があり、それ以来、吉井の歌碑を巡って人通りの少ない昼下がりの八尾の町を歩き回るのが私の日課となった。
吉井勇は伯爵吉井幸蔵の次男として明治19年東京で生まれた。早稲田大学中退後、新詩社に入り、「明星」に短歌を発表し、明治41年には「パンの会」を結成する。翌年「スバル」の創刊に参加し、耽美派の中心として活躍したが、のち人間の悲哀をみつめる作風に転じた。芸術院会員。昭和35年死去。74歳。
伯爵を返上したといえ、華族育ちで京都での生活の長かった吉井が、都から追われるが如くに北陸の片田舎にやって来た。まして大雪の年だった。雅に慣れた目には八尾はいかほど鄙に見えて寂しかったことだろう。
「大雪となりし高志路のしづけさは深深として切なかりけれ」
「雪はただしんしんと降るものを何に唇噛み耐えてある身ぞ」
また、言葉に敏感な歌人にとって鄙の言葉はどれほど荒々しく聞こえたことだろう。
「耳につく高志の訛りの濁み声もやうやく馴れて雪は深しも」
「蚤よりも人の心をむざと刺す寒き言葉をむしろにくまむ」
繊細な心は傷つき、昔の友を懐かしみ、酒を飲んでは孤独を癒すばかりだったのだろう。
「さむざむと夜半の寝酒飲み居れば炬燵の火さえいつか消えける」
「あわれなる流離のわれや欠椀のにごり酒にも舌鼓打つ」

流刑者の心情のようだ。後の「私の履歴書」に八尾で人情の酷薄さに悩まされたとの一文があるが、これは八尾の人々には酷だろう。戦争で人の心は荒んでいたであろうが、彼は当時60歳、異郷で人に心を開くには余りにも老いて、その頑な心で感じた八尾の印象だったのだろう。彼を慕って歌碑を多く建てた八尾の人々の情が酷薄であるはずがない。「寒行」の末尾や617首の「流離抄」を読むと、老いた歌人の寂しさがひしひしと伝わってくる。雪の降る寒い夜、彼の傍らに座り、言葉少なに酒を酌み交わし、彼の心を慰めたくなる思いがするのは私だけであろうか。
立野幸雄